Webデザイナーの仕事の探し方は色々です。就職エージェントを使ってWeb制作会社へ就職するのが最も一般的ですが、それ以外にも活躍の場はたくさんあります。
僕のように制作会社は経験せず、他業種の企業のWeb担当を経験したのちにフリーランスになるルートもあるわけです。
ここでは、未経験からWebデザインの仕事を得る方法を5つ紹介していきます。
- スクールの就職サポートを利用する
- 転職エージェントを利用する
- インハウスデザイナーの求人を狙う
- クラウドソーシング、ココナラで仕事を請ける
- ブログを運営してスキルを売る
①または②がもっともオーソドックスで、誰もが通る就職ルートです。サラリーマンWebデザイナーです。
③〜⑤はより自由度は高いですが、収入は不安定。実力と人脈次第で大きく羽ばたけるコースです。
以降で一つずつ詳しく解説していきましょう。
「若さ」があるか否かで選択肢の幅は大きく変わる
少し前置きします。
若さによって就職ルートは全然違うということは理解しておいてください。
30歳前後まではどこでも働ける、なんでもやれる
若い人の就職先はいくらでもあります。30前後までは大丈夫でしょう。これから先、いっそう人材不足になるのでなおさらです。
専門学校やWebデザインスクールを卒業したばかりの業界未経験者でも、若さがあればどこでも採用される可能性はあります。
中小企業のWeb担からWeb制作会社、広告代理店、大企業のWeb事業部など選択肢に困ることはないでしょう。(もちろん待遇はスキルに依存しますよ。)
30代中盤以降は腕で勝負
問題はこちら。歳をとればとるほど選択肢が狭まるのは確実です。
僕は36歳という絶望的な年齢でWebデザイナーになりましたが、制作会社や広告代理店などは初めから絶対無理と自覚していました。なので、はじめは安い案件でも請けて実績を積んで、腕を磨いてすぐにフリーになってやろうと思ってました。
フリーランスで食えるくらのスキルがあれば、年齢は関係なくなります。
30代中盤以降からWebデザイナーを目指すなら、まずキャリアパスを明確して戦略的にスキルアップしていく必要あるでしょうね。若い人より意識高めでWeb業界に入らないと生き残れないです。
① Webデザインスクールの就職サポートを利用する
Webデザインスクールでは受講生に就職先を斡旋しているところが多いです。就職保証があって「就職できなければ授業料返金」を謳うスクールもあるくらいです。
スクールはWeb業界とのコネクションを作る場でもある
スクールでWebデザインを学ぶ人は、スクールの就職・転職サポートを利用しましょう。これを使わない手はないです。
IT・WebスクールはたいていWeb業界と繋がっていて、企業がスクールの学生向けに求人案件を回していたりします。また、講師が現役または元Webデザイナーというケースも少なくないです。
オンラインスクールでもフリーランスWebデザイナーが講師やメンターだったりします。
スクールはWebデザインスキルを学ぶだけでなく、ツテや人脈の構築も期待できる場所です。
転職サポートが充実しているWebデザインスクール
就・転職サポートがしっかりしているスクールを紹介します。
返金保証まであるスクールは授業料が高めですが、裏を返せばカリキュラムの質が高くスキルの育成に自信がある学校とも言えます。安めのスクールで中途半端なスキルを身につけるより良いでしょう。授業料の差額は就職すればすぐに元が取れます。
WebCamp PRO(ウェブキャンププロ)
WebCamp PROは、転職・就職保証型のIT・Webスクールです。 「コース受講完了後、3ヶ月以内に転職・就職できない場合は全額返金」が保証されています。料金は498,000円と安くないので、まずは無料カウンセリングを受けることをおすすめします。
WebCamp PRO|転職保証付きプログラミングスクールTECH::EXPERT(テックエキスパート)
TECH::EXPERTは転職率97%を誇る即戦力エンジニア養成プログラム。こちらも「転職できなければ全額返金」を掲げています。こちらも料金は448,000円と高め。無料カウンセリングが用意されていますので活用しましょう。
TECH::EXPERT|未経験のITエンジニア転職なら
② IT・Web系の転職エージェントを利用する

IT企業やWeb制作会社、広告代理店などでWebデザイナー・エンジニアの仕事に就きたいなら、転職エージェントを利用するのが最も一般的で無難です。
就職・転職エージェント&キャリアコンサルタントを使い倒そう
現時点でやや実力が足りなくとも、早めにエージェントに登録しておくとメリットがあります。
キャリアコンサルタントに相談すれば、Web業界の事情や求められてる人材・スキルなどを教えてくれますし、新規の未公開案件も優先的に紹介してくれる可能性も高いです。
今現在、IT・Webの人材は不足の傾向にあるので、エージェントからしてみても早めに人材を確保しておきたいウェルカムな状況です。親身にあなたのキャリアパスを考えてくれるでしょう。マッチング(採用)に成功すればエージェント側も報酬が得られるので、どんどん案件を紹介してくれます。
IT・Web業界で優良な転職エージェント

IT・Webのクリエイター専門の転職エージェントは多数あります。それぞれ持っている案件も異なるので複数に登録しておくとよいでしょう。
レバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web専門の転職エージェントで、知名度と信頼性の高さでもっともおすすめ。エンジニア・クリエイターの就職・転職なら「とりあえずはここ」というくらいの安心感。
業界トップクラス4,000件超の求人登録数、非公開求人数も多数。職務経歴書の添削、模擬面談で事前準備も徹底サポートしてくれる。また、フリーランス専用エージェントのレバテックフリーランスも用意されていて、豊富な業務委託案件を紹介してくれる。
Geekly(ギークリー)
GeeklyもIT・Web業界専門転職エージェント。大手を中心に非公開求人数は2000以上で独占求人案件も多数ある。転職希望者のスキルや経験、職種経験をもとに多角的に分析して優良なマッチングを提案してくれるのが魅力。
Geekly(ギークリー)マイナビクリエイター
マイナビクリエイターは、Webデザイナー・クリエイター専門エージェント。業界専門のキャリアコンサルタントが転職をサポートしてくれる。会員には無料でポートフォリオ作成サービス「MATCHBOX」も提供している。
上記以外に、IT・Web特化でなくても大手のエージェントならWebデザイナーの求人案件も豊富に持っているのでこちらもチェックしよう。
3. 「インハウスWebデザイナー」の求人を狙う

WebデザイナーにはインハウスWebデザイナーという選択肢もあります。
インハウスデザイナーとは企業のWeb担当者のことです。
Web業界に限らず、他業種の事業主(例えば建築事務所や病院など)が自社でWebデザイナーを募集しているケースがあります。小規模な企業ならたいてい一人です。
「全てが自分の責任」という緊張感と貴重な経験が得られる
僕もインハウスデザイナーを2年経験しました。
僕個人としての感想は、「Web周りの全責任を自分一人で負う緊張感は大きかったけれど、得られた自信も大きかったので良い経験だった。」です。やってよかったです。このときの経験がフリーランスになった今も生きてます。
インハウスデザイナーのメリットはWeb周りを全て一人で担当できること、に尽きるでしょう。デザイン、Web開発、サーバー保守、SEO、Webマーケティング全てを一人で担当し全責任を負います。
制作会社なら先輩や同僚が手を貸してくれるかもしれませんが、インハウスWebデザイナーの場合、たいてい周りは専門外の人ばかりなのでトラブっても当然助けてくれません。
結果、自分でなんとかしなきゃという緊張感と自覚が芽生え、自ずとスキルアップしていきます。
フリーランスを目指す人には超おすすめの選択肢です。
インハウスWebデザイナーの仕事探しは一般的な求人サイトで
インハウスデザイナーをやるならWeb業界ではなく他業種の職場で働く方が面白いです。
インハウスデザイナーの求人は、IT・Web系の転職エージェント経由より一般的な求人サイトで地域の求人案件を探すといいです。ハローワークでもあります。
「Indeed (インディード)」などの求人サイトをのぞいてみると「Webデザイナー募集!!」案件がたくさん見つかります。
また、企業サイトの「採用ページ」でWebデザイナーの求人を掲載していることもあるのでチェックしてみると面白いですです。「あの会社、Webデザイナー募集してないかなー」なんてワクワクしながら職探しをする楽しみもあります。
インハウスWebデザイナーは給与が安い傾向
最後に一点、インハウスデザイナーのデメリット。給与が安い。
特に他業種の求人案件では、Webデザイナーは専門職という認識がなく、一般的な事務職やパートと同じレベルで給与設定されていることが多いです。
4. クラウドソーシングやココナラで仕事を請け負う
クラウドソーシング大手の『CrowdWorks(クラウドワークス)![]() 』などでは、Webサイトやバナーデザイン制作の案件が毎日掲載されていて、登録さえすれば誰でも応募できます。
』などでは、Webサイトやバナーデザイン制作の案件が毎日掲載されていて、登録さえすれば誰でも応募できます。
クラウドソーシングの案件は単価が安いので、これだけで生計は立てることは難しいけれど、初心者デザイナーがとにかく実践をこなすにはいい練習場になります。下積み、または副業という位置付けで考えれば、利用価値はとても高いですね。
僕自身もスクールに通いながらアウプットの場として、半年間Lancers(ランサーズ)を使い実務経験をつんでいました。初めて自分のデザインが売れたときは嬉しかったし、この頃に作ったWebサイトやバナー作品は今でもポートフォリオに掲載しています。
同様に、自分のスキルが売れる『ココナラ![]() 』というサービスもあるので、こちらを利用しても良いです。
』というサービスもあるので、こちらを利用しても良いです。
5. ブログを運営してスキルを売る
ブログを通して自分のスキルを売るという選択肢もあります。つまり、インターネット上で自分をWebデザイナーとして宣伝するという方法です。セルフブランディングというやつです。
日々ブログでデザインに関する情報や作った作品を発信し続けることによってファンを集め、サイト制作やデザインカスタマイズ等の依頼を募集します。
ただこの手段は短期間で成果を出すのは難しいですし、いきなり初心者がはじめても誰も依頼してくれません。ネット上で露出してある程度認知度が高まってかつスキルアップするまではかなり時間もかかるでしょう。
趣味または、自分のアウトプットの場という位置付けでブログを継続的に更新して信頼を積んでいけば、徐々にデザインやWebサイト制作の依頼も増えてくる可能性はあると思います。僕もこの方法で仕事を得ているWebデザイナーを何人か知っています。
就職活動前にまずはポートフォリオを作成しよう
Webデザイナーの仕事探しの前には、まずはポートフォリオを作ったほうがいいです。Web制作会社や広告代理店などでは必須のところが多いです。
ポートフォリオとは、これまでに自分が制作したWebサイトやバナーなどの作品集のことです。作品を片っ端から集めればいいというものではありません。自信作だけをまとめて公開します。
ただ、職種や仕事の探し方によってはポートフォリオは不要なこともあります。上で紹介したインハウスWebデザイナーなんかは、ほぼポートフォリオチェックなんてないでしょう。採用側がポートフォリオって何?っていう状態ですからね。
また、初心者がいきなりポートフォリオと言われても難しいかもしれないですね。ポートフォリオがなくてもWebデザインの仕事に就けないわけではないので、学びながら実績を積んでいけばよいと思います。





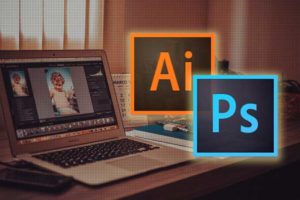




コメントを残す